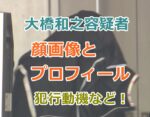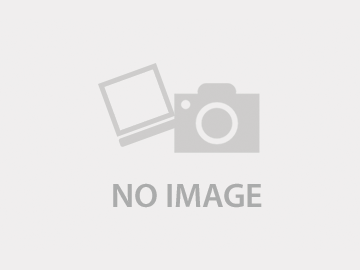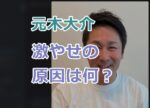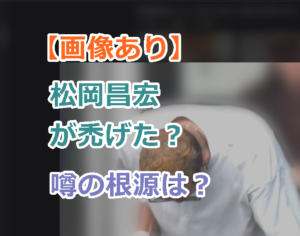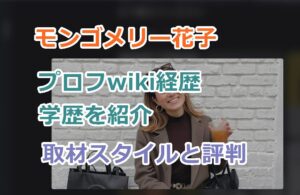大相撲の取り組みでは、時に判定を巡って議論が巻き起こることがあります。
2025年11月21日の大の里と安青錦の一番でも、物言いがつかなかったことに疑問の声が上がりました。
一部では誤審ではないかとの指摘もありますが、果たしてその真相はどうなのでしょうか。
本記事では、この取り組みを振り返りながら、物言いがなかった理由について考察します。
クリックできる目次
【動画】 大の里と安青錦の勝負の流れ
2025年11月21日に行われた大相撲九州場所の13日目では、横綱・大の里と関脇・安青錦の間で注目の対決が繰り広げられました。
この試合は両者が2敗で並ぶ中での直接対決であり、優勝争いにおいて非常に重要な一戦でした。
試合の流れ
試合は、立ち合いから大の里がもろ手突きで前に出る展開となりました。
安青錦は左上手を取るも、土俵際での攻防が続きました。
最終的に、大の里が寄り切りで勝利を収め、11勝目を挙げました。この勝利により、大の里は優勝争いの首位を守ることができました。
試合の際どい場面では、安青錦が土俵の外に飛び出す一方で、大の里も倒れ込むように見えましたが、審判からは物言いがつかず、大の里の勝ちが認められました。
安青錦は試合後、「自分の中では負け」と潔く認め、敗因を分析しました。
選手のコメント
試合後、大の里は「勝ったと自信があった」と語り、連敗からの復活を喜びました。
一方、安青錦は「土俵の外に飛んでいたので、負けたんだろうな」と冷静に振り返り、次回に向けての意気込みを示しました。
この結果、安青錦は3敗に後退し、優勝争いから一歩後退する形となりましたが、両者の今後の戦いにも注目が集まります。
大の里と安青錦の取り組みでネットでの疑問の声!
大の里と安青錦の取り組みにおいて物言いがつかなかった理由について、ネット上では多くの疑問の声が上がっています。
特に、安青錦が土俵の外に飛び出した際の状況が注目され、審判の判断に対する意見が分かれました。
主な反応と理由:
・審判の判断
高田川審判長は「物言いはつけようがない。安青錦が飛んでいるし、大の里が吹っ飛ばしたから」と説明しました。
この発言から、審判は安青錦が土俵の外に出たことを重視し、勝負が大の里に軍配が上がるのは妥当と判断したことが伺えます。
・視聴者の疑問
SNS上では、「この場面で物言いをつけても良かったのでは?」という意見が多く見られました。
特に、解説者の舞の海氏も「物言いをつけてもよかったのでは」と述べており、視聴者の間でも微妙な勝負だったとの認識が広がっています。
このように、物言いがつかなかったことに対する疑問は、審判の判断基準や試合の際どい状況に起因しており、今後の議論の余地が残されています。
物言いがつかなかった理由は死に体と判断されたから?
物言いがつかなかった理由について、
ネット上では「死に体」との判断が影響したのではないかという意見が見受けられます。
具体的には、安青錦が土俵の外に飛び出した際、大の里も倒れ込んでおり、どちらが先に土俵に触れたのかが微妙な状況でした。
相撲で「死に体」と判断される状態とは?
相撲における「死に体」とは、力士が体勢を崩し、立ち直ることが不可能な状態を指します。
この状態になると、相手の攻撃によって体が浮いてしまったり、重心を失っているため、勝負が決まったと見なされます。
具体的な特徴:
・体勢の崩れ
力士が相手の攻撃を受けて、体が前のめりになったり、横に傾いたりしている状態。
・土俵との接触
足の裏が土俵に触れず、他の部分が土俵に接触している場合、特に足が完全に土俵の外に出ていると「死に体」と判断されます。
・復元力の喪失
力士が自力で体勢を立て直せない状態であり、相手に対して反撃することができないと見なされます。
このような状態は、審判や行司の判断に委ねられ、明確な基準は存在しませんが、一般的には「死に体」とされると、その時点で負けが決まります。