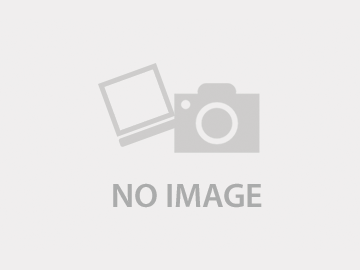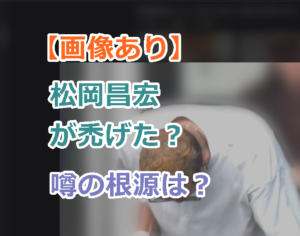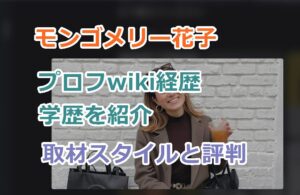「従三位」という言葉は、日本の位階制度における重要な位置を占めています。
この位は、正三位の下、正四位の上に位置し、古代から近代にかけて多くの著名な人物がこの位を授けられてきました。
本記事では、「従三位」の読み方やその意味、さらに具体的な使い方について詳しく解説します。
歴史的背景や文化的意義を理解することで、より深くこの位階の重要性を感じていただけることでしょう。
「従三位」の読み方なんと読む?
「従三位」の読み方は「じゅさんみ」です。
この読み方は、位階制度における一つの位を指し、正三位の下、正四位の上に位置します。
位階制度は、古代日本の官僚制度において重要な役割を果たしており、従三位は公卿と呼ばれる高位の官人に与えられる位の一つです。
このように、従三位は日本の歴史や文化において特別な意味を持つ位階であり、特に平安時代の貴族社会においては重要な地位を示すものでした。
「従三位」の意味!
「従三位」とは、日本の位階制度における一つの位を指します。
読み方は「じゅさんみ」で、正三位の下、正四位の上に位置します。この位は、古代から近代にかけての官僚制度において重要な役割を果たしており、特に公卿と呼ばれる高位の官人に与えられることが多いです。
意味:
・従三位は、位階の中で第三位にあたるもので、主に貴族や高官に授与されます。
・歴史的には、従三位以上の位を持つ者は「公卿」と呼ばれ、特別な地位を示します。
・また、従三位に叙せられた者が亡くなった場合、一般的な「死去」という表現ではなく、「薨去」と称されることがあります。これは皇族と同様の扱いを受けることを意味します。
このように、従三位は日本の歴史や文化において特別な意味を持つ位階であり、特に平安時代の貴族社会においては重要な地位を示すものでした。
「従三位」の使い方!
「従三位」の使い方について説明します。
1. 位階としての使用
「従三位」は日本の位階制度における一つの位であり、主に公職に就く者に与えられます。例えば、歴史的には高位の官職に就く者がこの位を持つことが多く、特に平安時代以降は「公卿」と呼ばれる貴族の中でも高位に位置づけられました。現代では、勲二等を受けた者が死後に「贈従三位」として叙位されることが一般的です。
2. 具体的な例文
- 「長嶋茂雄さんが死後に従三位を贈られることが決定した。」
- 「彼は戦前に陸軍大将として従三位に叙せられた。」
- 「従三位は、国家に特に功労のあった方に対して授与される栄典の一つです。」
3. 歴史的背景
「従三位」は、古代から近代にかけての日本の官僚制度において重要な役割を果たしてきました。位階は、朝廷が個人に与える格式や栄誉を示すものであり、従三位はその中でも特に高い地位を示します。
このように、「従三位」は日本の歴史や文化において特別な意味を持つ位階であり、さまざまな文脈で使用されます。