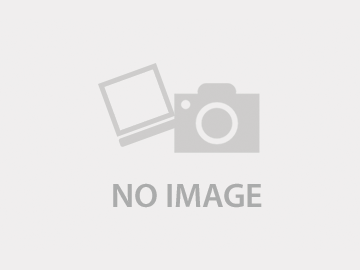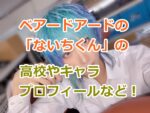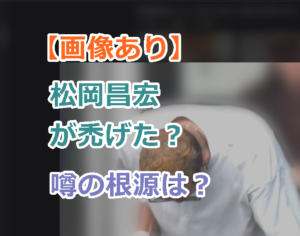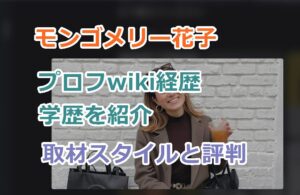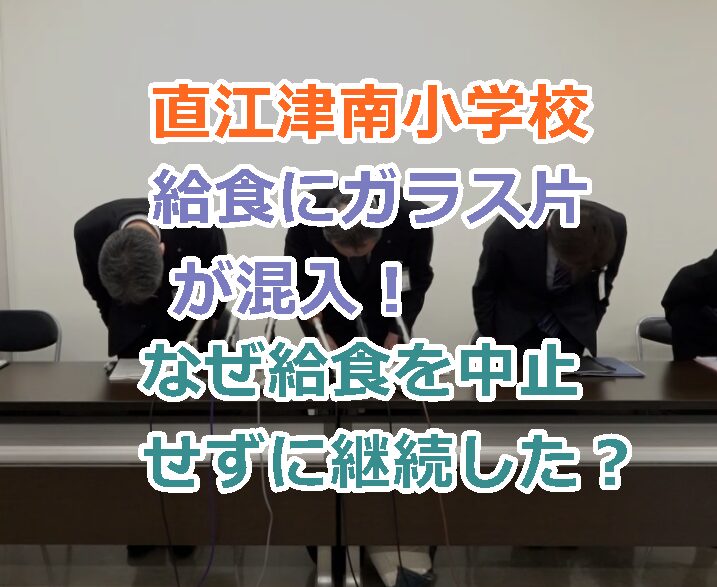
2025年4月22日
新潟県上越市の市立直江津南小学校で、給食に割れた蛍光灯のガラス片が混入する事故が発生しました。
この危険な状況にもかかわらず担任教諭と介護員は
給食を中止せず継続したことが問題となっています。
クリックできる目次
新潟の直江津南小学校で給食にガラス片混入事件の詳細

新潟県上越市の市立直江津南小学校で、給食に割れた蛍光灯のガラス片が混入する事故が発生しました。
この事件は2025年4月22日に起こり、以下のような詳細が報じられています。
事故の経緯
・蛍光灯の破損: 給食の配膳中、教室内に立てかけられていた蛍光灯が割れ、その破片がマーボー豆腐やご飯の食缶に混入しました。割れた蛍光灯は、黒板の横に置かれており、介護員がそれに接触して破損したとされています。
・給食の提供: 担任教諭と介護員は、目視で食缶を確認し、ガラス片を取り除いた後、そのまま児童に給食を提供しました。この時、児童2人がガラス片を口に含む事態が発生しましたが、給食は中止されずに続行されました。
・児童の反応: 児童の中には「ガリッとした」と訴える者もおり、別の児童がご飯の中にガラス片を見つけるなどの報告がありました。
教育委員会の対応
・事件発生後、上越市教育委員会は保護者に対して説明と謝罪を行い、
今後は異物混入が疑われる場合には給食を確実に中止するよう全小中学校に通知しました。
また、再発防止策を講じるための取り組みを指示しています。
健康への影響
幸いにも、事件発生時点で体調不良を訴えた児童はいないとのことですが、
今後の健康管理については注意が必要です。
教員がガラス片を取り除いた後、なぜ給食を継続した?

新潟県上越市の直江津南小学校で発生した給食に割れた蛍光灯のガラス片が混入した事件において、
教員がガラス片を取り除いた後に給食を継続した理由について考察します。
危機管理意識の欠如
教員や介護員は、目視でガラス片を取り除いた後、給食を続行する判断を下しました。
この判断は、異物が完全に除去されたと信じたためか、
または給食の提供を優先する意識が働いたためと考えられます。
市教育委員会の発表によると、
担任教諭は「危機管理意識や危険だという想像力が欠けていた」と述べています。
これは、異物混入のリスクを過小評価していた可能性を示唆しています。
業務の継続優先
教員が給食を継続した背景には、業務の円滑な進行を重視した結果があるかもしれません。
給食の時間は、児童にとって重要な日常の一部であり、
教員はその時間を維持することが教育的にも重要だと考えた可能性があります。
このような状況下で、異物混入のリスクを考慮するよりも、
給食を続けることが優先されたと推測されます。
過去の経験や慣習
教員や介護員が過去に異物混入の際に給食を中止しなかった経験があった場合、
その慣習が影響を与えた可能性もあります。
異物が混入した場合でも、目視で確認し、取り除けば問題ないという誤った認識があったかもしれません。このような慣習は、教育現場における安全管理の意識を低下させる要因となります。
情報の不足
教員や介護員が異物混入に関する最新の指導や通知を十分に理解していなかった可能性も考えられます。
市教育委員会は、異物混入が疑われる場合には給食を中止するよう通知していたにもかかわらず、
実際の対応がそれに従わなかったことは、情報の伝達や理解に問題があったことを示唆しています。